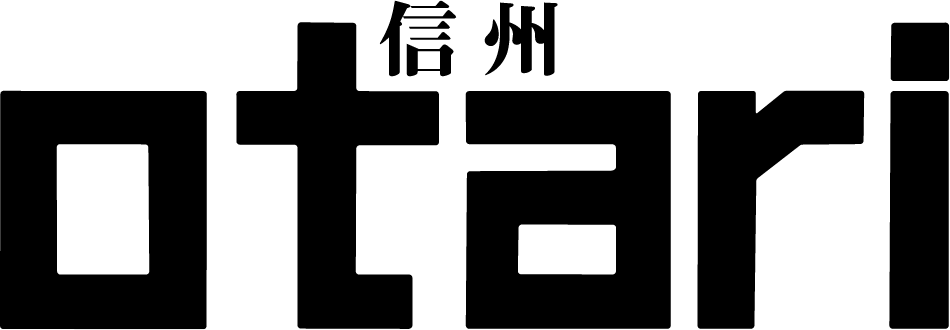日本海側から太平洋側へ、古くは塩や海の物を運ぶための交易路だった塩の道。村内の各コースはいずれも保存状態がよく、安全にトレッキングを楽しめます。大網峠越えや地蔵峠越えは本格的な「登山」となりますので、しっかりとした装備と余裕をもった行動時間が必要になりますのでご注意下さい。
千国越え

「塩の道祭り」でも歩かれ、モデルコースの中で最も整備されており安心して歩ける道です。牛と牛方が一緒に寝泊まりした「牛方宿」や「千国番所跡」「小谷村郷土館」など、往時の文化や歴史に触れるポイントが多く、塩の道の入門には最適のコース。行程全体が下り坂となる松沢口からのスタートがおすすめです。





行程
約20分 約25分 松沢口をスタート。前山百体観音から北アルプスの山々を望みながら平坦な道を進み牛方宿へ。
約35分 約55分 牛方宿から親坂を大きく下り、千国の集落から千国番所跡へ。
約65分 約50分 千国番所跡から千国諏訪神社 ![]() ・源長寺を通過して大別当へ。
・源長寺を通過して大別当へ。
約60分 約60分 大別当から小土山石仏分群を通過、山夜坂を下れば小谷村郷土館に到着。
交通
JR時刻表
大峯越え

大峯越えコースは和平別れから高町越えコースの始点を結んでいます。7年に一度行われる諏訪大社の薙鎌打ち神事道でもあり、諏訪信仰にまつわる遺構が多く見られ、古の雰囲気が味わえます。幾つかの集落を結ぶ道は小谷村らしい雰囲気を残しつつ、洒落たカフェや店舗などを同時に楽しめるコースです。





行程
約70分 約60分 和平の分かれから宮本橋を渡り番場・御頭岩などを経て緩やかに登るとガニ原に到着。
約45分 約30分 ガニ原から舗装路を登り、中通から静かな傍道を進んで土谷諏訪神社へ。
約20分 約10分 土谷諏訪神社からやや急な小径を登っていくと石仏が建つ大峯峠に到着。
約70分 約90分 峠からは一気に下り長崎へ。さらに県道を進むと市場(中谷局前郵便局)に到着。
交通
村営バス時刻表
高町越え

古くは大和王権時代より、姫川で採取されたヒスイを全国へ運び出す際に使用されました。また、諏訪大社御柱祭りの前年に行われる薙ぎ鎌打ち神事の舞台となるなど、見所が多いルートです。風雨鎮護を願い、信越国境にある御神木に薙ぎ鎌を打つ際の奉献品が通ることから、諏訪信仰が色濃く残る道になっています。





行程
約10分 約10分 市場から村道を進むと僅かな距離で中谷大宮諏訪神社に到着。
約60分 約40分 大宮諏訪神社から耳尾沢沿いに進むと山道となり明才堰跡を通過、緩やかに登れば埋橋に到着。
約60分 約65分 埋橋 ![]() から緩やかな下り始めると銭上平を通過、戸井笠沢から尾根道を下ると深原集落に到着。
から緩やかな下り始めると銭上平を通過、戸井笠沢から尾根道を下ると深原集落に到着。
約25分 約35分 深原からは舗装路を一気に下り北小谷駅へ。
交通
JR時刻表
石坂越え

小谷村の姫川西岸に点在する集落を結んで北上するのが石坂越え。対岸に雨飾山を望みながら、各集落と二つの峠を越えて進んでいきます。また、砂防のメッカと呼ばれる小谷村の砂防事業をよく観察できる道でもあり、浦川橋から望む稗田山大崩落と直轄砂防堰堤群は圧巻!様々な視点から楽しめる変化に富んだコースです。





行程
約50分 約50分 小谷村郷土館から虫尾薬師堂などを経て峠を越えると下里瀬に到着。
約50分 約40分 下里瀬から難所として知られたフスベを通過、経塚を見て下れば池原に到着。
約70分 約60分 池原から峠を越えて下ると石坂 ![]() から浦川橋を渡り、松ヶ峯へ登り返して再び下れば来馬集落に到着。
から浦川橋を渡り、松ヶ峯へ登り返して再び下れば来馬集落に到着。
約90分 約90分 来馬から緩く舗装路を下り北小谷駅へ。
交通
JR時刻表
天神道越え

古の雰囲気を色濃く残すのが天神道越えです。一方、真那板山の山体崩壊や蒲原沢土石流災害地など、災害史の縮図が垣間見れます。コースは歩きやすく、春にはカタクリの花が咲き、ヒメギフチョウが舞う光景が見られます。また、城の越の三峰様は盗難・火除けの神様として知られており、今でも大切に守られています。



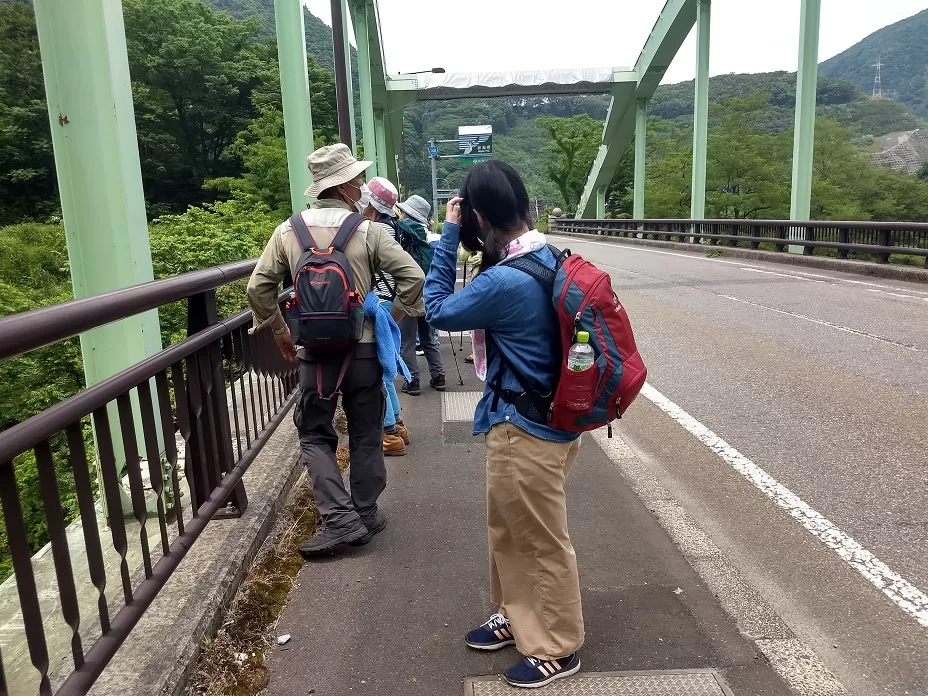

行程
約60分 約40分 北小谷駅から道の駅おたり ![]() ・島鉱泉・唐沢の石仏を通過、緩やかに登ると城の越に到着。
・島鉱泉・唐沢の石仏を通過、緩やかに登ると城の越に到着。
約40分 約50分 城の越から細かなアップダウンを繰り返しながら砂山を通過、大きく下ると湯原集落に到着。
約50分 約40分 湯原から猫鼻石仏群・蒲原沢を通過、ここから大きく登ると葛葉峠に到着。
約30分 約50分 葛葉峠から真那板山を望みながら舗装路を下ると平岩駅に到着。
交通
JR時刻表
大網峠越え

江戸時代の中期から荷継ぎ場所として栄えた大網集落と越後の山口宿を結ぶ古の峠道です。大網峠への道程には多くの道祖神や石仏が安置され、峠越えの過酷さを物語っています。長く急な登りか続くことから今でも上級者向けのコースとして知られていますが、変化に富み、特に秋の紅葉は目を見張る素晴らしさです。





行程
約50分 約40分 現在、この区間は土砂崩落のため通行止め。
約150分 約145分 大網から横川吊橋を渡り、菊の花地蔵・雪椿廊下・ウトウの道をたどると大網峠に到着。
約45分 約60分 大網峠から大きく下ると雨飾山を正面に望む白池に到着。
約50分 約70分 白池から一本杉を通過、さらに下ると山口(塩の道資料館)に到着。
交通
糸魚川バス時刻表
地蔵峠越え

奈良時代、和田の黒曜石や糸魚川の翡翠などを運んだ道が地蔵峠越えです。半年間は雪に閉ざされる峠道は大網峠越え同様、上級者向けの厳しい行程となりますが、所々から望む絶景、数多く残る石仏など、味わいのある道になっています。また、乱世における武田家・上杉家にまつわる逸話も多く残る道でもあります。





行程
約35分 約25分 北小谷駅より舗装路を登ると深原集落に到着。更に林道を登り深原口へ。
約95分 約70分 深原口より緩やかな小径をたどると地蔵峠に到着。
約160分 約180分 地蔵峠から僅かに下り、沢沿いに登れば大峠に到着。ここから大きく下ると長者平に到着。
約110分 約150分 長者平からはひたすら林道を下り、大網集落を過ぎれば平岩駅に到着。
交通
JR時刻表
鳥越峠越え

起点となる横川集落は海と陸を結ぶ重要な拠点でした。また、途中にある境の宮は、諏訪大社御柱祭の前年に行われる「薙鎌打ち神事」の開催場所です。このように、新旧の時流が混ざり合った独特の文化が形成され、他では味わえない雰囲気を感じられます。なお、峠道の途中から幻の峠「粟峠」への分岐があります。





行程
約70分 約60分 長者平から下り横川集落跡を通過、地すべり地帯の不安定な道を進むと殿行に到着。
約40分 約30分 人の往来で掘れたウトウを歩き、粟峠への分岐を通過すると鳥越峠に到着。
約45分 約55分 鳥越峠から下ると長野県で唯一、海が見える集落と言われる戸土廃村に到着。
約50分 約70分 戸土から舗装路を大きく下ると山口に到着。
交通
糸魚川バス時刻表
塩の道 三館めぐり

塩の道・千国越えコースの行程中には「小谷村郷土館」「千国の庄資料館」「牛方宿」の各資料館がコース上に点在しています。当時の歴史や雰囲気を感じるためにも、ぜひお立ち寄り下さい。



牛方宿
当時、牛方が宿泊していた施設が現保存された施設です。牛方の暮らしぶりなどを垣間見ることができ、三館の中で、当時の雰囲気を最も感じられる施設となっています。
0261-71-5610
千国の庄資料館
千国関所跡にある史料館です。塩の道に関する物と当時の暮らしぶりが知れる物品が展示されています。
休憩所が併設されており、よい立ち寄り処になっています。
0261-82-2536
小谷村郷土館
郷土館は塩の道に関わらず、村の歴史や民俗に関する資料を数多く展示しています。土沢で発見された恐竜の足跡の化石や岩石なども展示対象になっています。
0261-82-3663
入館料
各施設
大人 300円 ※中学生以下は無料
三館共通券
大人 500円 ※中学生以下は無料(団体は15名以上:一般 240円 小・中学生 無料)
休館日
火曜日(12-4月中旬の冬期は休館)